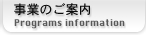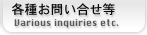2000年11月号(No.577)
- 巻頭言:ジェンダーの呪縛からの解放とは/清水真砂子
- 研究レポート:女子高校生の職業意識・進路状況および高校家庭科における進路指導のあり方について/佐藤由佳
- 女性施設クリップぼ〜ど: 男女共同参画社会を目指す出前講座/宝塚市立女性センター
- シネマ女性学:『老親ろうしん』日本映画(112分)
「自立と介護をさわやかに」/松本侑壬子 - 活動情報(1):「公立高校男女共学」を目指して/高橋久仁子
公立高校男女共学を実現する会 - 活動情報(2):「男女の役割それでいいの?」セミナーを実施して/ガールスカウト日本連盟新井妙子
- Women's View:
どうつける?「生活的自立」の力/合原理恵
生活に活用できるカウンセリング・マインド/山本静江 - このひと:今井嘉江さん―シャーロック・ホームズ代表ー
- きょうのキーワード:男女雇用機会均等対策基本方針
- 資料情報:2000(平成12)年度「学校基本調査」速報
巻頭言
ジェンダーの呪縛からの解放とは
清水真砂子(しみずまさこ)
アーシュラ・K・ル・グウィンの「ゲド戦記」第4巻『帰還』をどう読むかは、読み手自身がどれくらい成熟したフェミニズムに達しているか、どれくらいジェンダー・フリーの意識をもちえているかを明らかにして、誠におもしろいのだが、この作品の中に性的役割分担の問題で実に端的に書かれているところがある。
第1巻『影との戦い』の、少年時代からずっと男性の間でばかり生きてきて、暮らしの中に女性のいなかった主人公のゲドは、食器洗いも繕い物も自分でするのが当然と心得ていて、その技術も習得しているのに、女主人公のテナーの息子ヒバナは自分の使った食器の後片付けは女の仕事と考えていて、流しに運ぶことさえしない。テナーはそんな息子をゲドと比較して、育て方を誤ったと後悔するのである。
一方、家事をするのは当然と考えることのできるゲドも、過去のすべての地位・権力・名誉を失うことには耐性ができていない。それで、過去を思い、現在の自分を思って、無念と屈辱についつい愚痴っぽくなる。それを見てテナーは「女は屈辱なんて慣れっこになっているのに」と口には出さないが、思う。
「そう、そのとおり!」。わたしはここに思わず拍手をしたくなったものである。
ただ、このあとが違う。作中テナーは愚痴を言うゲドを受け入れるが、女たちの多くは自分たちの愚痴には寛容なのに、男の弱音、愚痴には、手のひらを返したように不寛容になる。これはどうしたことだろう。男女共同参画を提唱するのも悪くない。だが、女たちが、稼ぎを含めた力によるかっこよさを男に期待し続けるようでは、双方ともジェンダーの呪縛から自由になるのはまだまだ先のことではないだろうか。
プロフィール
1941年生まれ。児童文学者。青山学院女子短期大学教授。産経児童出版文化賞、日本児童文学者協会賞等を受賞。児童文学を中心とする翻訳・評論の分野で活躍。
主な著訳書は『子どもの本の現在』(大和書房)、『家族の現在』(共著,大和書房)、『家族はどこまでゆけるのか』(共著,JICC出版局)、『ゲド戦記』4部作(岩波書店)、『夜が明けるまで』(岩波書店)、『アウトサイダーズ』(大和書房)他多数。