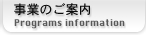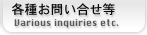2002年2月号(No.592)
- 巻頭言:きらめく星座の下で/宮下忠子
- 研究レポート:健康・開発とジェンダー/青山温子
- 学習情報クリップぼ〜ど:「子どものワークショップ−こころとからだの劇あそび」(もりおか女性センター)
- シネマ女性学:『落穂拾い』
フランス映画/アニエス・ヴァルダ監督
ミレー名画とリサイクル/松本侑壬子 - 活動情報(1):市民を育てエンパワーメントする
くろいそ女・男セミナー/佐藤由紀子 - 活動情報(2):障害児と共に地域で生きる
「沼田手をつなぐ親の会」の活動から障害者問題を考える/浅沼静恵 - Women's View:
男女共同参画のワークショップを重ねて さらに、新たな連帯と出会いを/菅村美知子
DV被害者に寄り添って/根本佳志子 - このひと:山極清子さん((株)資生堂ジェンダーフリー推進事務局・人事部課長)
- きょうのキーワード:GAD(ジェンダーと開発)
- 資料情報:第2回青少年の生活と意識に関する基本調査
シネマ女性学
ミレー名画とリサイクル
松本侑壬子・ジャーナリスト
『落穂拾い』(フランス映画/82分/アニエス・ヴェルダ監督)
大御所アニエス・ヴェルダ監督のドキュメンタリーである。力量ある監督というものは劇映画でもドキュメンタリーでも見応えある映画を作るものだなあ、とうれしくなってしまう。監督の社会へ向けるまなざしが半端じゃない。好奇心の塊がさらなる好奇心を呼んで、問題意識がぐんぐん展開して行く…。
題名は、かの有名なミレーの名画から。くどいようだが、この映画は面白いものを撮っているから面白いのではなく、平凡に見えるものが監督のまなざしによって面白くなるのである。
ある日、監督は市場で捨てられた物を拾う人を見て「拾うこと」への関心を呼び覚まされる。拾う動作はまるでかの名画『落穂拾い』の中の農婦そっくりだ。連想から好奇心を掻き立てられた監督は、ハンディ・カメラを片手に現代の落穂拾いを探して旅に出る。街から車を駆ってミレーの絵の舞台たる農場へ。画面いっぱいに地平線までうねる畑はフランスが豊かな農業国であることを印象づける。だがその豊かな農業国にも、現在飢えに苦しむ人たちがいるのである。
トラクターによる大規模農業の畑には、機械の取りこぼしや規格外れで捨てられたジャガイモやカリフラワーが1日に何トンも捨てられている。監督はこうした畑の片隅で野ざらしにされた野菜を拾って生活している人々と知り合いになり、飽くなき好奇心で捨てる側、拾う側双方からさまざまな事情を聞き出し驚いたり感心したり。1人でジャガイモを120キロも拾って車で持ち帰る人もいれば、ボランティアで救貧グループのために拾い集める人もいる。捨てる側にも協力的な農場、厳しく禁ずる法学者などさまざまだ。
監督は取材の合間に畑でハート形をしたジャガイモを見つけて大喜び。持ち帰って食卓に乗せて記念撮影。つくづく眺めると1個のジャガイモだっていとおしい。手軽なハンディ・ビデオカメラのせいだろうか、監督の心の動きが身近に伝わってくる。時には片手のカメラをもう一方の自分自身の手に向け超クローズアップで撮影してみる。70歳を越えた手のシミやシワを正視し老いについて考えるのだ。快いこととは言えまいが、彼女には曖昧さや“きれいごと”は通用しない。納得いくまでコトの本質をカメラを通して追求せずにはいられない。
旅の途中では本当にいろいろな人や物事に出合う。なぜかボクシンググローブを首から下げた犬、並んで走るトラックの車体の絵や文字が気になる、偶然知り合ったワイン農場主は何と!映画芸術の先駆者マレーの子孫だった。廃品を集めてシュールなオブジエや家まで造る無名の芸術家たち。大学院修士課程を出てボランティアで読み書きを教えているという青年は食べ物はすべて拾ったもので賄っている!
そもそも監督がこの映画の撮影を思い立ったのは、あまりにも多くの人が市場中を捨てた物を探して歩き回り、ごみ箱を漁る姿を見た“感動”からだった。くずは誰が、どうやって利用するのか――好奇心の赴くままに小型デジカメで捕らえた人物や光景が、映画の終わるまでには“無用な物”の問い直しという大テーマへと収斂していく。それは実はミレーの時代から変わらぬリサイクル思想なのだが、そのことをカメラで発見してゆく喜びこそこの映画の最大の魅力である。