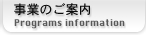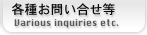2002年5月号(No.595)
- 巻頭言:もたれ合うのではなく、支え合う関係を求めて/田代和美
- 研究レポート:育児支援が親子関係、子どもの発達に及ぼす影響/加藤邦子
- 学習情報クリップぼ〜ど:講座「わたしがわたしであるために」西宮市男女共同参画センター
- シネマ女性学:『マッリの種』
インド映画/サントーシュ・シヴァン監督
テロリストの少女の真実/松本侑壬子 - 活動情報:文句なしに楽しい、心ふるえること?それは「みゅーじかる!」
みゅーじかる劇団きんちゃい座/中山須美子 - 活動情報:「カラリス in SAGA」って何?−誕生して10年目の課題/西村緑
- Women's View:
「女性の学習の歩み」研究セミナーで得たもの/山澤和子
啓発活動の難しさ。“ジェンダー・フリーへの近道”ってある?/藤田羊 - このひと:山岡テイさん(情報教育研究所代表)
- きょうのキーワード:高齢社会対策大綱
- 資料情報:平成14年度文部科学省女性教育・家庭教育に関する予算のあらまし
シネマ女性学
テロリストの少女の真実
松本侑壬子・ジャーナリスト
マッリの種(インド映画/99分/サントーシュ・シヴァン監督)
世界のあちこちで血なまぐさいテロ事件が後を絶たない。最近では自爆テロの実行犯として年若い女性や少女の名が挙げられるのが気になる。
この映画は、1991年インドのラジブ・ガンジー首相を自爆テロで暗殺した少女テロリストをモデルにしている。本作で長編劇映画の監督デビューしたS.シヴァン監督は、事件をニュースで知って「自分の腹の回りに爆弾を仕込んだベルトを巻くとは、一体どんな人間なのか。彼女を思い止まらせることはできなかったのかとの疑問から映画化の着想を得た」と語っている。インドのマドラスを中心に撮影期間わずか3週間、製作費予算は5万米ドル(約650万円)という超低予算の小品であるが、見る者に与える感動は無限である。
事件とは違う結末には、シヴァン監督の祈りともいうべき人間観が込められている。それは「生命(いのち)」への気づきである。「生命が、ある」と実感した者には、自分の命も他人のそれもおろそかにはできない。敵を殺すことだけを教えられて育った少女に「生命」の存在を気づかせたものは―。
マッリは19歳。物心ついたときから、ある集団に属し、テロリストとして育てられた。父親は高名な愛国派詩人、兄は使命のために毒をあおって自殺した英雄として名を残した。組織では自分自身の感情や思考を持つことを許されず、すべて組織の命令に従って行動し“正義”のために死んで英雄となることだけを人生の目的としている。
大きく見開いた瞳、鼻も口も大きく、意思的な美しい少女だ。組織の裏切り者をあっさりと処刑し、目前の敵を眉一つ動かさずにマシンガンで撃ち殺す。冷静沈着で美しい殺人マシーンのようなマッリは仲間の少女たちの尊敬と羨望の的だ。ある日、組織からあるVIPを暗殺する「考える爆弾(=人間爆弾=自爆テロリスト)」を求める指令が届く。選ばれたマッリは組織のリーダーと食事を共にする栄誉を得た後、1人任地へ向かう。
暗殺への旅はマッリにとって生まれて初めて組織の外の世界と接する機会でもあった。最初の道案内人は虐殺の生き残り孤児だった。地雷に怯える少年を労わるマッリを少年は姉のように慕う。だが、遭遇した敵を平然と撲殺するマッリの姿は少年を恐怖と絶望に陥れる。マッリを呆然と見送る少年の悲劇はそれで終わらない。水と緑の美しい映像の中のあまりに痛ましいエピソードだ。
暗殺の舞台となるべき町に着いたマッリは、農業研修生として陽気な老人宅に下宿する。老人は長年寝たきりの妻の世話をし、カメラマンだった亡き息子の部屋をマッリに提供する。壁の無数の老若男女の写真はマッリに人間の多様性を語りかける。老人はマッリの正体を見抜きながらさりげなく種蒔きに託して生命の大切さを語り、植物人間状態の老婆は信じられない力でマッリの手を握る。マッリは“普通の暮らし”の中からこれまで知らなかった感情や愛の存在を知る。そして、いよいよ使命遂行の日がきた…。
マッリの微妙な心理の変化を見事に捕らえた映像はインド屈指の名カメラマンでもあるシヴァン監督自身の撮影による。「政治情勢を変える力は映画にはない。ただできることは、人々の注意を喚起することだ」という同監督のメッセージは深く胸底に染みわたる。