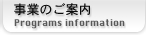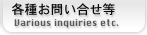2003年8月号(No.610)
- 巻頭言:悲しみを通して見えること/若林一美
- 【新企画】誌上アートギャラリィ:フォトエッセイ Jigsaw Puzzle 11/落合由利子
- 研究レポート:男女共同参画に対する最近のバックラッシュについて/細谷実
- 学習情報クリップぼ~ど:女性のやきもの講座(武生市男女共同参画センター)
- シネマ女性学:『WONDERUNDERWATER/原色の海』
ドイツ映画(45分)/レニ・リーフェンシュタール監督
レニ100歳のメッセージ/松本侑壬子 - 活動情報(1):レッツゴーtothe議会!ENOSHIMA-V
- 活動情報(2):新世紀「阿波女の企業家たち」がはばたく
AWAおんなあきんど塾の活動/山本淹子 - Women's View:
求められる「家庭での性教育」/柳原信香
個々人が能力を発揮できる時代へ/伊藤千津子 - 今どき学習ウォッチング:つかず離れず・・・
- このひと:樋渡紀和子さん(オンブズマンみなと代表・港区区議会議員)
- きょうのキーワード:次世代育成支援対策推進法
- 新刊案内:男女共同参画時代における子育て支援者養成ガイド
- 【新企画】なるほど!ジェンダー:「産む、産まない」は私が決めることなのに・・・/イラスト:高橋由為子
巻頭言
悲しみを通して見えること
若林一美(わかばやしかずみ)
「ちいさな風の会」という、子どもを亡くした親の会が生まれて、今年でちょうど15年になる。この会が生まれた1980年代は、現在以上に、悲しみや痛みを表現することに対し、自他ともに抵抗が強かった時代である。「いつまでもメソメソしていたら死んだ人が成仏できない」「明るく前向きに生きるべきだ」など、一見「慰め」とも思える言葉が遺族の感情の表出を拒んでいた。同時に、遺族自身も「悲しんだからといって戻ってくるわけではない」「家の恥を話してどうなるのだ」と、悲しみを抱くことそのものを否定しようとしていたのである。
しかし愛する人が傍らからいなくなったとき、悲しむこと、涙を流すことは自然な感情であり、その思いを社会の中で共有することが大切である、という認識が、徐々にではあるが日本社会にも広まりつつある。私は25年以上にわたり、このような遺族や重篤な病を抱えながら生きている人、その家族の話を聞いているが、「悲しみ」に関して男性は、「社会的な役割」といったものに女性以上にしばられ、自分の正直な思いを素直に認めることが不得手のように思われる。そしてこのことが「子どもの死」という家族の危機に遭遇したときなど、価値観や感情の違いとして意識され、夫婦関係に亀裂を生じさせてしまうこともある。
十数人で始まった「ちいさな風の会」には、現在北海道から沖縄まで200人を超える会員がいるが、5~6年前から父である男性たちの参加が増えてきている。このほか際立った変化として、自死で子を失う親たちが増加しており、この傾向は年々強まっている。
死別の悲しみばかりではなく、もし人が生きていく中で抱える悲しみや痛みを社会で容認し合うことができれば、もう少し生きやすくなるのでは、と思えてならない。
プロフィール
1949年東京生まれ。山梨英和大学人間文化学部教授。「ちいさな風の会」代表。IWG(死と遺族に関する国際会議)会員。death study, bereavement care, grief, hospice など、死別や遺族のケア、悲嘆についての研究に取り組む。『死別の悲しみを超えて』(岩波現代文庫)、『亡き子へ』(岩波書店)、『悲しみを超えて生きる』(講談社)、『自殺した子どもの親たち』(青弓社)、翻訳『シシリー・ソンダース― 近代的ホスピス運動の創始者』(日本看護協会出版会)他。
いまどき学習ウォッチング
つかず離れず…
野外活動に参加したときのこと。初めて沢登りを体験した。前半は順調に沢を進むことができた。が、コース終盤になって突然大きな岩壁が立ちはだかった。そこを超えないとゴールにはたどり着けない。進むか後戻りするかは参加者の判断に任されている。
ロッククライミングなどやったことがない。どうするか…。意を決して登り始める。しかし、あと少しのところで足場を失い進めなくなった。万事休す!
とその時、「大丈夫!落ち着いてじっくり考えてごらん」との声。そう、落ち着いて、ゆっくり、右足、左手、左足…。一歩一歩、集中して這い上がる。やった!登れた!
自分の力で登りきった自信と充実感。しかし、つかず離れず見守ってくれた引率者の存在は大きい。直接手を差し延べるわけではない。必要な時に適切な助言をし、参加者自身の力を引き出してくれたその働きかけ。参加型学習でのファシリテーターのあり方が話題になる時、いつもこの体験を思い出す。