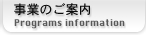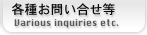2003年9月号(No.611)
- 巻頭言:地域・市民活動のエンパワーメントを/相川康子
- 【新企画】誌上アートギャラリィ:フォトエッセイ Jigsaw Puzzle 12/落合由利子
- 研究レポート:Welearn(ウィアンラーン)
−ジェンダーにかかわる再学習のプロセスを考える/森実 - 学習情報クリップぼ〜ど:地域活動実践セミナー「組織運営のための実践講座」(長野県男女共同参画センター)
- シネマ女性学:『夕映えの道』
フランス映画(90分)/ルネ・フェレ監督
熱く問う老いと友情/松本侑壬子 - 活動情報(1):ほどよい距離がここちよい地域の居場所づくり
「高齢社会の食と職を考えるチャンプルーの会」の試み/紀平容子 - 活動情報(2):自己変革から社会変革へ
行動・共感・つながり−SEANの取組/遠矢家永子 - Women's View:
女性問題をわかりやすくお見せしたい/佐々木裕子
ポルノグラフィ・買春は女性への人権侵害/春原ちさき - 今どき学習ウォッチング:2頭のロバの話から考えることは・・・
- このひと:清水靖枝さん(横浜市長屋門公園歴史体験ゾーン事務局長)
- きょうのキーワード:性同一性障害者性別特例法
- 新刊案内:第12回出生動向基本調査「結婚と出産に関する全国調査」(独身調査)
- なるほど!ジェンダー:こんなに低いの“なんでだろ”/イラスト:高橋由為子
巻頭言
地域・市民活動のエンパワメントを
相川康子(あいかわやすこ)
人はなんのために学ぶのか─。 純粋に知識を得る喜びや自己実現の要素もあるだろうが、突き詰めていえば「よりよい実践のため」ではないだろうか。市民活動の現場では、よいことをしているつもりでも、対象者や社会のニーズからずれていたり、目の前の事案に追われて、ほかの重要課題を見過ごす事例が少なくない。私のフィールドである阪神・淡路大震災の被災地では、市民団体が刻々と変わる状況に試行錯誤で対応してきた。緊急支援の役割を終えて解散した団体もあれば、コミュニティ・ケアなど次の課題に取り組む団体もある。どちらにもなれず、消えた団体もある。
絶え間ない学習は、活動の目的を明確にするだけでなく、そこに至るまでの道筋ややり方を問い直すために重要である。自分で必要な情報を集め、活動を評価し、限られた人材や資源をどう生かすのか優先順位を決めねばならない。市民活動と言えども、行政評価や企業経営とも共通する運営手法が求められている。
これまで「地域活動」の担い手は、主婦を中心とする女性で、領域も高齢者や子どものケア、リサイクルなどに限られてきた。ここでの「地域」は「男は外で働き、女は家を守る」という分業意識に基づく家庭の延長のようなものだ。しかし、地方分権の時代、「地域」の位置づけは、経済・環境・社会の3領域を統合する自律的な存在として変わりつつある。本来なら、市民活動の領域も、それに伴ってハード面の設計管理や市民事業の起業へと伸びるはずである。が、なかなかその兆しが見えない。
求められているのは、志と経済の両立であり、学習と実践のスパイラル的な発展だ。古い女性役割を乗り越えたところに、新しい地域・市民活動のかたちがある。
プロフィール
1965年生まれ。男女雇用機会均等法の1期生として、神戸新聞社に入社。記者や研究員を経て、現在は論説委員。関心領域は市民社会論、環境問題、女性問題など。震災後、被災地のNPOやコミュニティービジネスに関心をもち、その評価方法を学ぶべく神戸商科大学の大学院に社会人入学。個人的な活動として、特定非営利活動法人 NPO政策研究所理事、自治体学会運営委員など。
シネマ女性学
心に染みる老いと友情の物語
松本侑壬子・ジャーナリスト
『夕映えの道』(フランス映画/90分/ルネ・フェレ監督)
原題は「ルトレ通り」。でも、パリの地理に詳しくない身には、この邦題の方がしっとりとしたイメージが広がる。昨今の国籍不明、意味不明の題名の流行の中では抜群に名訳だ。世代を超えた女同士の友情の物語が、すみずみにまで心配りの行き届いたタッチで心に染みるように描かれる。パリで企画・広告会社を経営する中年女性イザベルは、偶然町の薬局で一人暮らしの老女マドと知り合う。古く懐かしい風情を残すルトレ通りにあるマドのアパルトマンを訪れて愕然とする。雑然と足の踏み場もない室内。押入れは薄汚れた洗濯物やがらくたであふれ、そこら中に悪臭が漂う。しかし、誇り高いマドは市の福祉サービスを頑として受け入れない。自分の生活を他人にかき回してもらいたくないというのだ。これが老いて一人で暮らす現実なのか。
同じ一人暮らしながら、広く居心地のいいしゃれた家に住むイザベルは、離婚した元夫とは仕事上では協力し合ういい関係、息子のような年下の恋人がいて、何人も社員を抱える会社は順調。忙しいけれど、それだけに張り合いのある毎日。成功したキャリアウーマンの典型のようなイザベルは、これまで眼中になかった老いることの現実に衝撃を受け、マドのことが頭から離れなくなった。髪を短く刈り上げ、短めのパンツに大き目のワークシューズを履いたイザベルは、忙しい仕事の合間にマドの部屋の掃除や洗濯をしに通ってくるようになる。「あなたの自己満足のためでしょう」とのマドの憎まれ口に「そうよ」と居直り、渋るマドを病院に連れていく。実はマドはがんに侵されていて精密検査の必要があるのだが、彼女はイザベルの手配した看護師を拒否する。
イザベルは仕事を秘書に任せ、自分でマドの世話をすることにする。他人には頑ななマドだが、タオルで全身を拭いてくれるイザベルには心を許し、小声でお礼を言い、そして少しずつ自分の生い立ちを語り始める。不幸な子ども時代を経て帽子職人として働いていたころの話をするマドの目は輝き大切にとっていた自作の帽子を取り出して見せる。それはマドの生涯の宝物であり、かつてマドも働く女性の誇りと生き甲斐をもっていた証だった。
しかし、不幸な過去はマドの心に癒しがたい被害妄想を刻んでおり、その爆発を受け止めかねたイザベルは「もう、ありがた迷惑はやめるわ」と腹を立てて出ていく。 が、結局また戻ってくるのは、マドが何だか亡くなった母を思い出させるからだ。いや、自分の母との関係には悔いることばかりだったからこそ、マドには優しくしたいのだ。疲れ果て思わず椅子に座ったまま眠り込んでしまうイザベルの姿に、マドはイザベルもまた生活の重荷を背負っていることを悟る。実際、イザベルの日常は、夜ベッドに若い恋人を待たせたまま、隣室のパソコンで残った仕事を片づけるといったかなり重症の仕事人間だった。それが仕事を一切忘れてマドとかかわることでイザベル自身も自分自身を取り戻し、安らぎ、癒されている。
ルトレ通りの石畳を二人で散歩し、ベンチで休みながらマドがしみじみとつぶやく言葉、流す涙…。 静かなラストシーンが、友情とは、幸福とは、そして生き甲斐とは、を熱く問いかける。
いまどき学習ウォッチング
2頭のロバの話から考えることは…
ある参加型の学習の場でのこと。「2頭のロバが一本の綱で互いにつながれていた。少し離れた左右2ヵ所に干草がある。ロバはどうしたら餌にありつけるか」という問いが出された。大抵の人は、「2頭が一緒に移動すれば餌にありつける」と答える。しかし、参加型の学習では、答えは一つではない。参加者の人数分の答えがあってよいはずだ。「そもそもロバ同士がつながれているなんて変だ。綱を断ち切ればいい」という答えがあってもいい。
この2頭のロバの話から、私たちは何を連想するだろう。親子や夫婦、仕事の同僚など、一連托生の人間観件はさまざまだ。一方が他方の意に反して引きずって動くことは、意に反する側からみれば自由を制約されることになる。しかも誰かがつないだ綱のせいで…。
肝心なのは、2頭のロバがそれぞれ餌にありつき、自分の行きたい方へ行く自由を獲得するにはどうしたらよいかを考え合うことであり、参加者が協働することでたくさんの気づきが得られることである。問題の解決を考えるとき、思いやりや温もりといった個人的な感情世界に留めることなく、社会とのかかわり方を変えていく、そうした話し合いでは思わぬ自分を発見したりする。